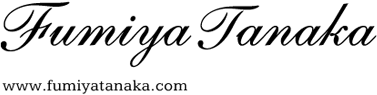BLOG
バイナルケース
April 30, 2016

バイナルケースは大きく分けて2種類あります。
約80枚入るスーツケース型のもの(ソフトケースを含む)、約40枚入るリュック・ショルダーバッグタイプのもの。
自分は約80枚入るソフトケースを使用していますが、プレイ時間の長さによって個数が決まります。
通常3時間未満のプレイの場合1ケース、プラスリュックサックで、約100枚ぐらいのレコード量です。
5時間以上のプレイの場合は2ケースで、約160枚ぐらいのレコード量。
重さにして50キロ近くあります。
移動の悩みはいつも重いレコードバックをどうするか。
重いレコードを諦め、デジタルに移行する時が来るのかもしれません。
レコードを諦める時はこれが唯一の理由になるでしょう。
ただレコードでずっと続ける、その考えは変わりません。
レコードはアートです。
レコードの音とデジタルの音では圧倒的に音の質感が違いますから。
みなさんにはレコードの音で音楽を体感してほしい。
これもレコードで続ける唯一の理由です。
レコードの音が好き、レコードでプレイする一連の作業、これも理由です。
余談ですが準備の段階でどうしてもバイナルの枚数が増えていくのも悩みです。
どれを削るか。
何を捨て何を諦め何を選択するか。
気持ちとしてはアイデアの手がかりを見つける為の必要なバイナルは出来るだけ持っていきたい、とは思います。
結果的に使わないバイナルも出てきますが、それはプレイ後に分かることで結果的に使わなかったバイナルは、あとの事後検証で必要になる。
ただ広げすぎにもよくない面があると思っています。
1人の人間が1度に把握出来る情報量には限りがあります。
選択肢が多すぎると迷いが出てくるし、どれもよく思えるものです。
あの時の迷いがミスの原因だったって気づくことはあるし、制限がある中でどうやりくりするか、現場での即興判断の醍醐味でもあります。
適量は1ケース分、レコード約100枚ぐらいです。
フロアーにレコードが選ばれる
March 31, 2016

フロアーにレコードが選ばれる、とはプレイ中に次にかかるレコードが自然に選ばれる、そのチョイスが迷いなく続いていく状態のことをいいます。
何もないところから段々とひとつの流れみたいなものが自然に出来上がっていく、その波のようなものを捕まえ乗る状態そのものがフロアーにレコードが選ばれる状態であるといえます。
言葉にするのはとても難しいのですが、DJプレイとはある程度の時間をかけて出来上がっていくもので、それはフロアーにいる人達そこに存在する全てのものとの共同作業でもあるといえます。
自分の存在などどうでもよくなり、忘れ、ただ浮かび上がってくる最善のレコードをチョイスし続ける。
そのレコードに導かれ、繰り返す時間と共に連続して起きていく現象がそれであり、その一部として即興選択に没頭するのです。
現象というとオカルトを想像しますが、決してオカルトなんかではなく、これは音楽を媒介にした即興集団アートです。
最善のレコードが何なのか、フロアにレコードが選ばれるとは何なのか。
自分でも正直よくわかっていません。
レコードが自然に湧き上がる状況が浮かび上がるのには時間が必要だし、今何が起きていてどんな音がなっているのか理解する力、またそこにコミットするための発想と構想が鍵になります。
特にプレイ序盤の的確な選曲、大胆な組み立てが重要で、その日のプレイをどこまで充実させられるかは序盤で決まってしまうと言っても言い過ぎではありません。
序盤の充実が中盤の広がりに繋がるし、中盤の充実が、多種多彩な終盤の選択を担保できる。
その指針となるヒントはフロアのあちこちにあり、それら全てを漠然と捉え、自分のアイデアとマッチングさせ浮かび上がってきたレコードこそ次にかかるべきレコード、最善のレコード、フロアーに選ばれたレコードだと思うのです。
俯瞰で見る
February 29, 2016

調子の波が悪い時に何をやってもダメな時があります。
私の場合は長い時でおおよそ3年間スランプが続いたことがありました。
調子を崩している時は、何らかの理由でアイデアや状況を俯瞰で見れなくなっており、自分の考えやアイデアに拘り過ぎて視野が狭くなっているものです。
調子が良い時はアイデアと状況を俯瞰で見れる瞬間が持続しますから、会場内で音が届いていないのではないか?というところにまで気を配れた選曲ができます。
逆に言えばそれが出来ていない時が調子が落ちてきている時で、落としきらないよう意識をします。
ただ調子の悪い時でも、悪いなりにやり切ることは大切です。
やりきることで調子を戻すことはあるし、その経験が必ず次の機会に活きているからです。
調子が悪い時は大体ひとり相撲を取っているので、その事に気付くことすら難しい。
調子が悪いと嫌になるし、どうしていいか分からなくなります。
そういう時は何もしないで休んだり、意識して視点を変えられる遊びや他のことをしてみるのもひとつです。
時には逃げてみましょう。俯瞰で見れるところに巡り着くかも。
調子の波
January 22, 2016

DJを続けていると調子の良い時と悪い時があって、調子の波みたいなものがあります。
相性の良い現場やムードというのがもちろんあって、それをきっかけに調子を上げることがあります。
もちろんその逆もあります。
実際の現場では抜群の音響環境でプレイ出来ることもあれば、機材トラブルに見舞われることも多々あります。
トラブルに奮起し結果的に調子を上げることもありますが、それを境に調子を落とすこともあります。
調子は知らず知らずのうちに崩したり上がったりします。
調子が良い時はそのままで構いませんが、調子を崩している時は何かをしなくてはなりません。
調子を崩している時はその波にあまり囚われず、基本に立ち返る事できっかけを掴むことがあります。
今までやってこなかったことにチャレンジしたり、自分の得意な形でやってみるのもひとつです。
調子の波は例えるとギターやベースのチューニングが気がつかないうちに狂ってる感覚です。
出来ればそのことに少しでも早く気づけばよいのですが、意識して狂いに気付こうとせず、続けながら狂いに気づいて調整するのが健康的です。
余談ですが調子の波が良い時におすすめなこととして、とことんやってみる、があります。
とことんやってみるとは、単に量の話で長時間DJをやる行為のことです。
これは調子の良い時にやるのが効果的で分かりやすいですが、とことんまでやると、どこかで調子を崩しかけるタイミングが必ず出てきます。
それが分かるのは調子が良いからで、またそこは改善ポイントでもあり課題でもあるので、その洗い出しに効果的です。
自分の場合は調子が悪い時でもとことんやってみる、をやりますが、調子が悪い中延々と続けていると、段々と調子を戻す、なんてことがあるからです。
長時間のDJをプレイして、結果的にやりきって調子を戻したなんてことは何度もあります。
耳やカラダ、感覚がトリートメントされるのです。
とことんまでやりきることは調子のバロメーターを測る上では効果的なアプローチで、ズレの間隔や調子の波の幅を出来るだけ小さくすることが、クオリティを保ち続けます。
事後の検証
October 20, 2015

基本的にはあまり変わっていませんが、プレイ中に選曲ミスしたところ、選曲中に選ばなかったレコードについて確認するのが事後検証です。
浮かび上がらなかった組み合わせのレコードを確認しながら、足りなかったレコード、必要のなかったレコードを洗い出します。
序盤の構想に改善の余地があるか、終盤の展開に工夫の余地がなかったかなど色々とわかってきますが、事細かくやるのではなく、出来る限り単純明解に結論付けます。
この結論も絶対という位置づけではなく、あくまでそうかもね、ぐらいの余地を残したまとめにします。
所詮は事後検証なので。
この作業は出来るだけ早いタイミングで行います。
プレイ後2,3日が妥当なタイミングで、次回の準備の際もう一度簡単に見返す作業にも繋げます。
出来るだけ早いタイミングで行うのは、気分的に肉体的にリフレッシュする必要があるからで、次回に向けて新鮮な気分で臨む為のモチベーション持続にコンディション調整は欠かせません。
若い頃はリフレッシュなど気にしたことがなかったですが、今はリフレッシュしないとカラダも気分もついてきません。
終わった事はさっさと忘れ、自分の中に空きスペースが出来るのを待ち、意識して関係のないことをします。
それでも四六時中音楽が頭から離れないので、そういう時は何もしないようにします。
ただ最近は何もしない時間などほとんど取れないので、意識して休暇を作ります。