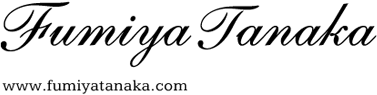BLOG
当たりをつける
June 30, 2016

バイナルケースの中にあるバイナルを1枚ずつ見て選曲するわけではありません。
それではどうやってプレイをしているのか?
どのレコードがどこにあるのか、ある程度当たりをつけている場所から決めうちで選曲しているのです。
当たりをつける場所とは大まかにまとめたグループの中からさらに大まかに区別している場所のことで、その作業自体はプレイ直前に現場で行います。
大体プレイが始まる15分ぐらい前から始めるのですが、そのことで集中力も同時に高まっていきます。
この時点で構想通りになるのか、ある程度モデルチェンジをするのか、予定していたアイデアをどうするかなど大体の方針を固めますが、この時にいくつかの組み合わせや全体のおおまかな組み立ても同時にイメージします。
ただ実際は始まって見ないとよく分からないので何も決めず、交代前のDJの前後の流れに気を配りながら、交代前のDJが最後にプレイしたレコードを聞いて初めて決めていきます。
どこにどのレコードがあるのか、プレイが始まるまでは同時にそれを頭に叩き込む作業にも集中します。
構想は念頭に置いて、でもそれに拘り過ぎず、次にかかるべきバイナルが何かを選択することに集中します。
この時頼りになるのは構想と直感で、迷いなく選曲出来る時もあれば、2、3枚のレコードを比較対象にする時もあります。
最初に浮かび上がったバイナルが選曲されることが多いですが、
DJを始めた頃はバイナルケースの中にあるバイナルを一枚ずつ見て選曲していました。
自分の構想に拘り片っぱしから手当たり次第プレイする、というようなスタイルです。
しかしそのスタイルでは日本では通用しても世界では通用しないことが段々分かってきました。
世界の文脈で自分の音楽をプレゼント出来ておらず、荒削りで穴だらけのDJだったのです。
今思えばDJを始めた頃のプレイは勢いに任せたプレイでした。
日本でしかプレイしたことがなかったことや、若さ故無知な部分が多かったのです。
しかしながら若さ特有の跳躍的な発想は、時にありえない組み合わせを可能にしたり、無知が故好奇心だけで無謀とも言えるところに躊躇なく手を伸ばしたり、怖いもの知らずで手当たり次第にいろんなことに挑戦できていたのです。。
それは若さの特権でもあるけど、残念ながらそれは永久には続きません。
人は必ず老いていくのでどこかで必ず壁にぶち当たります。
今では考えられない幅広いジャンルの音楽を一晩で選曲したり、見よう見まねであり得ない組み合わせの音楽を作ろうとしたり、そういう活動を通して今のスタイルのベースを意識的に無意識的に確立していったのです。
世界で通用するためには自分の拘りを進化させ、世界で意味のあるものにアップデートしていく必要があります。
若い時にしか出来ないDJがあるように、私のような年齢でしか出来ないDJがあります。
大まかにまとめ、当たりをつけ、即興で選曲するDJの面白みに取り憑かれているのは、手当たり次第に手を伸ばし平気でジャンルを横断した若い頃の蓄積が肥やしになっているのは間違いありません。
おおまかにまとめる
June 13, 2016

レコードをグループ分けにしてバイナルケースにまとめています。
大まかに3つぐらいのグループにまとめて入れるのですが、どんなリズムやメロディーか、どんなグルーブのキャラクターかなどを基準に大まかにまとめます。
自分の場合その都度発想したいくつかの構想から、アイデアにマッチするレコードを選曲しそれぞれを大まかにまとめていきます。
準備自体個性が出るし、このあたりもやりながら自分のアプローチを見つけるしかないのですが、若い頃はレコードを無雑作に入れていたことがよくありました。
それでは現場で対応しきれなくなることがわかると事前準備を怠らなくなりましたが、今となっては準備無しのぶっつけ本番を試しに一度やってみたい思いもあります。
次のバイナルに繋げるまでの与えられた時間はほんの数分。
その間に一挙に判断、選曲まで繋げるので、時間との勝負でもあります。
現場で直ぐに対応できるようバイナルケースのどこにどのレコードが入ってるのか、ケースの中を見やすくしておくのは工夫の一つです。
どんなテーマでグループ分けをしてもいいのですが、グループごとに大まかにまとめておくことは、次のバイナルをより早く見つける為の工夫でもあります。
バイナルケースの中に入っているレコードはおおよそ頭の中に入っていますが、それでも見落としや抜けはあるのです。
どこにどのレコードがあるのか、頭の中に叩き込むのです。
その他には想定外に備えたバイナルを準備することもあります。
ただ想定外はキリがないので、あくまでこれをやる時も大まかにまとめます。
その都度結論を出しながら大まかにまとめることは、他の可能性を残した余白を残している行為でもあり、きっちり決めないことでエラーを受け入れ、それに対処する術に頼るのです。
即興選択の連続で、実際現場は事前の想像を超えていきます。
これら全ての準備やまとめは、結局のところ現場での生の対応に不可欠なことであり、現場でアレンジされた形での表現こそ即興の醍醐味です。
パーティーにはたくさんの情報が溢れており、準備した構想、アイデアをそのまま形に出来ることなどあまり多くなく、それは生身の人間とのコミュニケーションだからでもあります。
自分の構想だけで出来上がった表現も素晴らしいと思いますが、外からの影響にオープンになりその場で構想をアップデートさせる行為が現象の側の構えです。
だからこそ事前準備はあくまで大まかにまとめるのです。
バイナルケース
April 30, 2016

バイナルケースは大きく分けて2種類あります。
約80枚入るスーツケース型のもの(ソフトケースを含む)、約40枚入るリュック・ショルダーバッグタイプのもの。
自分は約80枚入るソフトケースを使用していますが、プレイ時間の長さによって個数が決まります。
通常3時間未満のプレイの場合1ケース、プラスリュックサックで、約100枚ぐらいのレコード量です。
5時間以上のプレイの場合は2ケースで、約160枚ぐらいのレコード量。
重さにして50キロ近くあります。
移動の悩みはいつも重いレコードバックをどうするか。
重いレコードを諦め、デジタルに移行する時が来るのかもしれません。
レコードを諦める時はこれが唯一の理由になるでしょう。
ただレコードでずっと続ける、その考えは変わりません。
レコードはアートです。
レコードの音とデジタルの音では圧倒的に音の質感が違いますから。
みなさんにはレコードの音で音楽を体感してほしい。
これもレコードで続ける唯一の理由です。
レコードの音が好き、レコードでプレイする一連の作業、これも理由です。
余談ですが準備の段階でどうしてもバイナルの枚数が増えていくのも悩みです。
どれを削るか。
何を捨て何を諦め何を選択するか。
気持ちとしてはアイデアの手がかりを見つける為の必要なバイナルは出来るだけ持っていきたい、とは思います。
結果的に使わないバイナルも出てきますが、それはプレイ後に分かることで結果的に使わなかったバイナルは、あとの事後検証で必要になる。
ただ広げすぎにもよくない面があると思っています。
1人の人間が1度に把握出来る情報量には限りがあります。
選択肢が多すぎると迷いが出てくるし、どれもよく思えるものです。
あの時の迷いがミスの原因だったって気づくことはあるし、制限がある中でどうやりくりするか、現場での即興判断の醍醐味でもあります。
適量は1ケース分、レコード約100枚ぐらいです。
フロアーにレコードが選ばれる
March 31, 2016

フロアーにレコードが選ばれる、とはプレイ中に次にかかるレコードが自然に選ばれる、そのチョイスが迷いなく続いていく状態のことをいいます。
何もないところから段々とひとつの流れみたいなものが自然に出来上がっていく、その波のようなものを捕まえ乗る状態そのものがフロアーにレコードが選ばれる状態であるといえます。
言葉にするのはとても難しいのですが、DJプレイとはある程度の時間をかけて出来上がっていくもので、それはフロアーにいる人達そこに存在する全てのものとの共同作業でもあるといえます。
自分の存在などどうでもよくなり、忘れ、ただ浮かび上がってくる最善のレコードをチョイスし続ける。
そのレコードに導かれ、繰り返す時間と共に連続して起きていく現象がそれであり、その一部として即興選択に没頭するのです。
現象というとオカルトを想像しますが、決してオカルトなんかではなく、これは音楽を媒介にした即興集団アートです。
最善のレコードが何なのか、フロアにレコードが選ばれるとは何なのか。
自分でも正直よくわかっていません。
レコードが自然に湧き上がる状況が浮かび上がるのには時間が必要だし、今何が起きていてどんな音がなっているのか理解する力、またそこにコミットするための発想と構想が鍵になります。
特にプレイ序盤の的確な選曲、大胆な組み立てが重要で、その日のプレイをどこまで充実させられるかは序盤で決まってしまうと言っても言い過ぎではありません。
序盤の充実が中盤の広がりに繋がるし、中盤の充実が、多種多彩な終盤の選択を担保できる。
その指針となるヒントはフロアのあちこちにあり、それら全てを漠然と捉え、自分のアイデアとマッチングさせ浮かび上がってきたレコードこそ次にかかるべきレコード、最善のレコード、フロアーに選ばれたレコードだと思うのです。
俯瞰で見る
February 29, 2016

調子の波が悪い時に何をやってもダメな時があります。
私の場合は長い時でおおよそ3年間スランプが続いたことがありました。
調子を崩している時は、何らかの理由でアイデアや状況を俯瞰で見れなくなっており、自分の考えやアイデアに拘り過ぎて視野が狭くなっているものです。
調子が良い時はアイデアと状況を俯瞰で見れる瞬間が持続しますから、会場内で音が届いていないのではないか?というところにまで気を配れた選曲ができます。
逆に言えばそれが出来ていない時が調子が落ちてきている時で、落としきらないよう意識をします。
ただ調子の悪い時でも、悪いなりにやり切ることは大切です。
やりきることで調子を戻すことはあるし、その経験が必ず次の機会に活きているからです。
調子が悪い時は大体ひとり相撲を取っているので、その事に気付くことすら難しい。
調子が悪いと嫌になるし、どうしていいか分からなくなります。
そういう時は何もしないで休んだり、意識して視点を変えられる遊びや他のことをしてみるのもひとつです。
時には逃げてみましょう。俯瞰で見れるところに巡り着くかも。