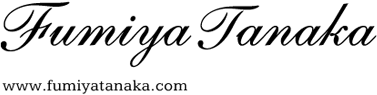BLOG
調子の波
January 22, 2016

DJを続けていると調子の良い時と悪い時があって、調子の波みたいなものがあります。
相性の良い現場やムードというのがもちろんあって、それをきっかけに調子を上げることがあります。
もちろんその逆もあります。
実際の現場では抜群の音響環境でプレイ出来ることもあれば、機材トラブルに見舞われることも多々あります。
トラブルに奮起し結果的に調子を上げることもありますが、それを境に調子を落とすこともあります。
調子は知らず知らずのうちに崩したり上がったりします。
調子が良い時はそのままで構いませんが、調子を崩している時は何かをしなくてはなりません。
調子を崩している時はその波にあまり囚われず、基本に立ち返る事できっかけを掴むことがあります。
今までやってこなかったことにチャレンジしたり、自分の得意な形でやってみるのもひとつです。
調子の波は例えるとギターやベースのチューニングが気がつかないうちに狂ってる感覚です。
出来ればそのことに少しでも早く気づけばよいのですが、意識して狂いに気付こうとせず、続けながら狂いに気づいて調整するのが健康的です。
余談ですが調子の波が良い時におすすめなこととして、とことんやってみる、があります。
とことんやってみるとは、単に量の話で長時間DJをやる行為のことです。
これは調子の良い時にやるのが効果的で分かりやすいですが、とことんまでやると、どこかで調子を崩しかけるタイミングが必ず出てきます。
それが分かるのは調子が良いからで、またそこは改善ポイントでもあり課題でもあるので、その洗い出しに効果的です。
自分の場合は調子が悪い時でもとことんやってみる、をやりますが、調子が悪い中延々と続けていると、段々と調子を戻す、なんてことがあるからです。
長時間のDJをプレイして、結果的にやりきって調子を戻したなんてことは何度もあります。
耳やカラダ、感覚がトリートメントされるのです。
とことんまでやりきることは調子のバロメーターを測る上では効果的なアプローチで、ズレの間隔や調子の波の幅を出来るだけ小さくすることが、クオリティを保ち続けます。
事後の検証
October 20, 2015

基本的にはあまり変わっていませんが、プレイ中に選曲ミスしたところ、選曲中に選ばなかったレコードについて確認するのが事後検証です。
浮かび上がらなかった組み合わせのレコードを確認しながら、足りなかったレコード、必要のなかったレコードを洗い出します。
序盤の構想に改善の余地があるか、終盤の展開に工夫の余地がなかったかなど色々とわかってきますが、事細かくやるのではなく、出来る限り単純明解に結論付けます。
この結論も絶対という位置づけではなく、あくまでそうかもね、ぐらいの余地を残したまとめにします。
所詮は事後検証なので。
この作業は出来るだけ早いタイミングで行います。
プレイ後2,3日が妥当なタイミングで、次回の準備の際もう一度簡単に見返す作業にも繋げます。
出来るだけ早いタイミングで行うのは、気分的に肉体的にリフレッシュする必要があるからで、次回に向けて新鮮な気分で臨む為のモチベーション持続にコンディション調整は欠かせません。
若い頃はリフレッシュなど気にしたことがなかったですが、今はリフレッシュしないとカラダも気分もついてきません。
終わった事はさっさと忘れ、自分の中に空きスペースが出来るのを待ち、意識して関係のないことをします。
それでも四六時中音楽が頭から離れないので、そういう時は何もしないようにします。
ただ最近は何もしない時間などほとんど取れないので、意識して休暇を作ります。
事前の準備
September 11, 2015

出かける前にやることは、22年間あまり変わっていません。
そのパーティーはどんなパーティーか、前回訪れた時にどうだったか、どんなプレイをしたかを思い出します。
ただ憶えていないことも多く、時間は流れてますから以前と同じ、なんてことはほとんどないですよね。
ですから今分かること、それだけを手掛かりにします。
最近の自分の傾向を照らし合わせ、今回の自分の方針を固めていきます。
実際に現場に行って感じた事を頼りにプレイしますが、事前に固めた方針の変更を迫られる事は日常茶飯事です。
事前の準備にこだわり過ぎない柔軟性が結局は指針になります。
元も子もありませんが、柔軟に対応できるのは、事前の準備があるから出来ることです。
加えて柔軟に対応する力はDJには不可欠です。
無駄かもしれない事前の準備は、結局のところ状況の変化に対応する為の基礎体力作りにもなっています。
四六時中音楽が頭にある自分は、事前の準備が日常です。
日常の遊びから事前の準備まで区別とボーダーが曖昧で、頼りになるのは日時だけです。
思考プロセス
July 2, 2015

次のレコードを選ぶ時DJは頭の中で何を考えているのか?
自分の場合前後の流れから次にどのレコードがかかるのが自然か、最善のレコードは何かを考えています。
その時に選曲されなかったレコードのかかる可能性についても考えている事がありますが、それは後の作業です。
浮かび上がった2、3枚のレコードの比較ですが、今現在と少しだけ先の展開をイメージすると最善のレコードが選ばれてきます。
今流れてるレコードとフロアの反応は常に変わりますから、その時の状況判断が重要になります。
状況に振り回されてもダメ。ブレないことが大切です。
仕掛ける構えは常に残します。
失敗の継続
May 2, 2015

ルーティーンで使っているレコードは一旦置いておいて、レコード棚に眠っているレコードだけでいちから選曲をすることがあります。
その時によく使っているレコードは基本的に選曲から除外します。
なぜこんなことをするのか?
普段使ってるレコードを繰り返し使い続けると、どうしても発想が窮屈になって飽きが来てしまいます。
気付かないふりをして続けてるとフレッシュな感覚やモチベーションを同じレベルで持続させていくのが難しくなっていくので、頭への刺激とアップデイトの為に試します。
うまくいっている時はついつい安全運転をしてしまうので、ルーティーンワークに陥っていても気づかなかったりします。
レコード棚に眠っているレコードを組み合わせると発見はあるし、同時に酷い目にもあう。
ぶっつけ本番なので失敗して当然ですが、失敗があまり怖く無いので、ついついやってしまいます。
失敗したから引き出しが増えたのか、失敗したと思ってるのは自分だけか、この辺りはよく分かりません。
心がけているのは調子が良いと感じている時でも変化していくことを選び、意識的に積極的に仕掛けていくことです。